2012.08.08 前日夕刻、八戸から新幹線に乗り東京へ着いた茫猿は東京に一泊し、この日は横浜に向かったのである。 横浜でのお目当ては、07.20に開館したばかりの「原鉄道模型博物館」訪問である。 原鉄道模型博物館へは、横浜駅東口からルミネ横浜を抜け、はまみらいウオークを行きますと横浜三井ビルが目に入ってきます。 ポルタ地下街を抜けても行けます。 博物館は横浜三井ビルの二階に開館しています。
博物館では、陳列されている模型の質と量に圧倒されました。 ジオラマもかつて観たことのないスケールとその完成度の高さに唸らされました。 個人の趣味の域を遥かに超えているものでした。


(左)横浜三井ビルのエントランスをくぐって目に入ったのが、博物館に通じるエスカレータ前の行列です。お盆前のこと、幼児や小学生を連れた祖父母、両親の行列が伸びています。
(右)博物館入場券売り場と、入り口です。写真撮影が許可されるのは、此処までです。広い一階ロビーの天井に開けられた丸い穴に吸い込まれてゆくエスカレータは、Hara Model Railway World への 入り口に相応しい ファンタスティックなものです。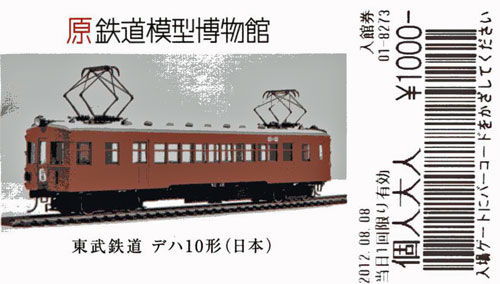
鉄道模型のスケールには幾つもの種類がありますが、日本で最も普及し一般的なのはNゲージです。 次いでHOゲージ Oゲージ Zゲージ 原鉄道模型博物館の主展示は一番ゲージです。
※Nゲージ:軌間9mm (レールの間隔) の鉄道模型(縮尺1/150)、HOゲージ:軌間16.5mm、縮尺1/80、Oゲージ:軌間32mm、縮尺1/45(0番ゲージともいう)。 原鉄道模型博物館が主に展示する一番ゲージは、軌間45mm、縮尺1/32でありGゲージとも称される。
茫猿鉄道は主力がNゲージで、その外周にHOゲージを配置している。 原鉄道模型博物館の主展示・一番テツモパークは、このHOゲージと比較して軌間で倍、縮尺もほぼ倍であるから、そのスケールの大きさに圧倒される。 ジオラマのスケールもさることながら、最も注目されることは展示される車輌模型の精密さである。 千輌にも及ぶという、展示されている膨大な数の模型車輌コレクションは、実車を正確に写し取った模型が多く、細部まで精密に作られていることに驚かされる。 なかで幾つか展示されている自作模型は、個人の趣味の域をはるかに超えており、原氏の造詣の深さに驚嘆させられる。
※ES-E626 電気機関車(写真、文章ともに原鉄道模型博物館サイトより引用)
この模型はBreda社製の1928年イタリア国鉄の縮尺約1/32の電気機関車で、世界に類を見ないレベルまで忠実に実車を再現したものです。全体の組み立ても、実車と同様に組枠を作って、それに屋根、側面、端面を結合する作り方になっています。材料は洋銀。ハンダ付けは一切なく、全部リベットとビスで製作されています。外部に面した開口部はすべて開閉でき、しかも、内側にはレバーによる開閉装置がついているなど、忠実に実車を再現されている。


この一番テツモパークで最も驚いたのは、車輌の動力供給方式である。 一般にNゲージもHOゲージも動力供給は線路を通じて行う、SLや気動車などを除く、パンタグラフを持つ電車模型も架線から動力を得ることはせず、線路から動力を供給するのである。 その意味でパンタグラフは装飾的意味しか持たない。 しかし、Hara Model Railway World :一番テツモパークでは架線から電気を供給しているのである。 安定した走行ができるように、架線をしっかりと架設することは、1/32模型とはいえとても難しいことであるし、メンテナンスも大変であろうと想像できる。 それ故に、一番テツモパークの素晴らしさが引き立つし、驚かされるのである。
ただただ驚かされる原鉄道模型博物館であるが、氏の経歴を知れば、1930年代(氏が小学生の頃)から、鉄道や鉄道模型に親しむことができた氏の生い立ち、そして、その後も鉄道模型ファンとして過ごすことのできた原氏の人生に、尊敬の念と同時にある種のうらやましさも感じた、Hara Model Railway World 訪問でした。
関連の記事
- 茫猿鉄道2020 -3- : 2020年1月21日
- 鉄道模型・ジオラマ : 2005年10月22日
- 梅小路閉館!!! : 2015年7月24日
- 鉄道模型フェア : 2008年1月22日
- 櫻と鉄道模型 : 2007年3月28日
- 鉄道模型&相談会の風景 : 2003年10月2日
- 第六期茫猿鉄道廃線 : 2010年8月29日
- 茫猿鉄道復興に着手 : 2003年5月14日
- ジオラマを観る : 2011年6月29日
- 茫猿鉄道・動画No.001 : 2010年3月27日
